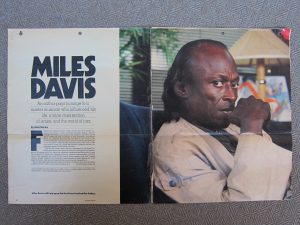1週間ほどヘルシンキに行ってきた。日本とは国交100年というめでたい年、秋篠宮ご夫妻の訪問の3日位後だったが、別にこれは偶然。北極圏にすぐのところにあるサヴォリンナの15世紀の古城でオペラも観劇したし、途中の道端で野生のブルーベリーも摘んで食べたし、もちろんジャズも楽しめた。
夏の長い夜は、中央駅から歩いて10分くらいのStoryville にてSpirit of New Orleans(SONO)というグループを聴いた。ニューオーリンズ出身のトランペット奏者リロイ・ジョーンズをフィーチャー。このグループではトランペットとボーカルも提供。90年代はハリー・コニックのビッグバンドなどで活躍していたが、ルイ・アームストロングなどニューオーリンズの伝統に根差したジャズを展開している人。
SONOのリーダーはカチャ・トイボラ、フィンランドのトロンボーン奏者。1975年生まれのフィンランド人です。彼女はニューオーリンズ・プリザベーション・ホールで定期的にプレーする最初の女性管楽器奏者と言われている。トラッドなジャズに興味をそそられ、彼女は1990年代からニューオーリンズを度々訪問し、そしてリロイ・ジョーンズと結婚。

2005年にハリケーン・カトリーナがニューオーリンズを襲ったとき、多くのミュージシャンがそうだったように、彼らも厳しい状況が続いたが、徐々に活動を広げていき、SONOとして、そしてニューオーリンズヘルシンキコネクション(NOHC)というユニットとして、カチャの故郷であるヘルシンキで年に数回、そして海外でも(ニュージーランドなど)公演をしている。
肌寒い夏の夕べだったけれど、なかなかのグルーヴイーな演奏で、良かった良かった。なかでも、ピアノの女性がタッチが良く、只者ではないなと思い、ファースト・セットが終わったところで、リーダーのカチャにインタビュー。Digerius のおすすめ10枚にしっかり入っているリータ・パーキだった。最初の1曲でファンになってしまった。
カチャに君たちのグループのお薦めCDを教えてよと言ったら、日本から来たと言ってあったこともあり、2枚のCDを在庫の入っている箱から出してきた。1枚はピアノの渡辺真理さん参加の「マホガニー・ホール・ストンプ」。 究極のCDのタイトル。 これはルイ・アームストロングの最も人気のある曲の一つ。 1929年に大恐慌の年の録音。 エイント・ノーバディーズ・ビジネスAin’t Nobody’s Business(1956年のカーネギー・ホール・コンサートでビリー・ホリデイが歌ったもの)、セント・ルイス・ブルースなどスーパー・クラシックも入っている。 もう一つは、ユニットNOHCによる「パラダイス・オン・アース」。 尾崎ノブがベースで参加。 アルバム・タイトルでオープニング・チューンのパラダイス・オン・アースはカチャのペンによるとっても素敵な心温まる一曲。
渡辺真理は早稲田大学ニューオルリンズ・ジャズ・クラブ出身で、1985年にニューオーリンズに移住し、以来現地で人気を博している。現在Chosen Few Jazz Bandチョウズン・フュー・ジャズバンドのリーダー(「選ばれた数少ない」っていうバンド名はすごいね)。
ニューオーリンズの音楽はとにかく深くて広い。ジャズバンドはまた、ブラスバンド(ダーティ・ダズン・ブラスバンドがすぐに頭に浮かぶ)、マルディグラ・インディアン音楽(現在はニューオーリンズ・ファンクとして知られている。ミーターズが代表的)、プロフェッサー・ロングヘア、アラン・トゥーサント、イギリス生まれのジョン・クリアリーなどのニューオーリンズ・スタイルのピアノ。ニューオーリンズ・ファンクはあんまり知らないが、他の分野はそこそこ聞いている。でもぼく的には、長年の興味はニューオーリンズで子供時代を過ごしたランディ・ニューマンかな。ルイジアナ1927、ニューオーリンズが戦争に勝利する、などの曲。
トラッド・ジャズ(ディキシーランド・ジャズやニューオーリンズ・ジャズを含む総称)では、1960年代からの日本の先駆者、例えば外山喜雄・恵子夫妻はトラッド・ジャズを学び演奏するために“移民船”でニューオーリンズに行っている。トラッド・ジャズのハートとソウルのある本場に学びに行き、地域や音楽に慣れるという伝統があるようだ。外山のような先導者たちの努力と彼らの音楽に対する愛情は、地元のプリザベーション・ホールの関係の人々との信頼の輪につながっているのだろう。なにしろ、外山夫妻はほどなくジョージ・ルイスやキッド・トーマスと一緒に演奏していたのだから。この辺の事情は小川隆夫の「言葉で綴る日本のジャズ」に詳しい。
セットリストとメンバーは
1. Undecided
2. Bye Bye Blackbird
3. On Sunny Side of the Street(以下のvideoは許可取得済。アップロードの制限等技術的問題をクリアしようとしてますが、現状では不鮮明なのでお許しを)
4. Ain’t Gonna Give Nobody None of My Jelly Roll
5. Georgia on my mind
6. It’s Only a Shanty in Old Shanty Town
Katja Toivola (tb)、Leroy Jones(tp, vo)、Riitta Paaki(p), Teemu Keranen(b), Mikko Hassinen(ds)
Storyville, Helsinki, July 13, 2019